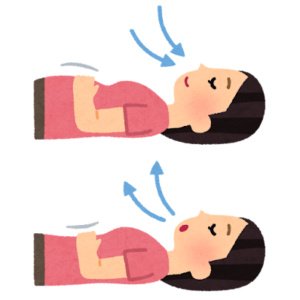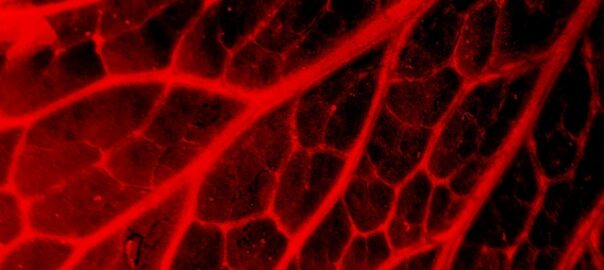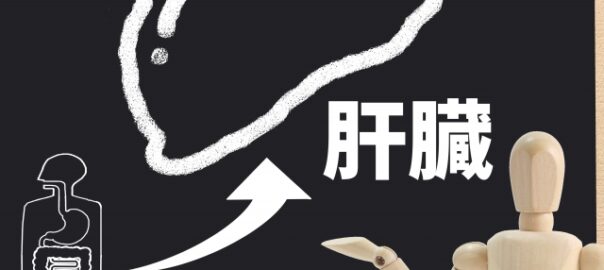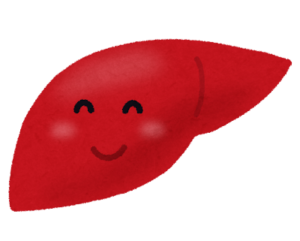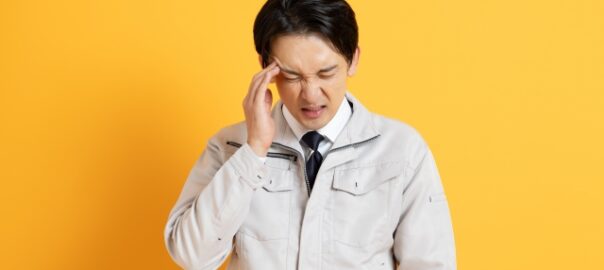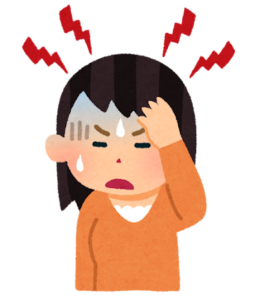3月の脱水症状に注意!
寒さが和らぎ、水分補給を怠ると脱水症状を引き起こしやすくなる
春の訪れを感じ始める3月。冬の厳しい寒さが和らぎ、日差しも徐々に暖かさを帯びてきます。この季節の変わり目は、私たちの体にも少なからず影響を与えます。その中でも特に注意したいのが、「脱水症状」です。
「脱水症状」と聞くと、猛暑の真夏を思い浮かべがちですが、実は春先の3月も、脱水リスクが高まる時期のひとつなのです。なぜこの時期に脱水症状が起きやすいのか?そして、どのように予防すべきかを詳しく解説します。
なぜ3月に脱水症状が起きやすいのか?
1. 気温上昇による発汗増加
3月は寒さがやわらぎ、気温が徐々に上昇してきます。それに伴い、体温調節のために汗をかく機会が増えます。しかし、まだ冬の延長線上にいる感覚が残っており、「汗をかいている」と自覚することが少ないため、水分補給を怠りがちになります。
2. 暖房による乾燥
室内では引き続き暖房器具が使われていることが多く、空気は乾燥したままです。乾燥した環境下では、皮膚や呼気を通じて体内の水分が知らず知らずのうちに奪われていきます。呼吸による水分の喪失は意外に多く、特に乾燥した部屋に長時間いることで脱水が進行することがあります。
3. 花粉症や風邪による水分消耗
3月は花粉症の症状が本格化する時期でもあります。くしゃみや鼻水、鼻詰まり、目のかゆみなどの症状で、体内の水分が多く消耗されます。また、風邪をひくと発熱や下痢、嘔吐などによっても水分を失いやすく、知らないうちに脱水状態に陥ることも少なくありません。
脱水症状のサインを見逃さない!
軽度の脱水でも、体にはさまざまな変化が現れます。以下のような症状が見られたら、脱水の可能性を疑ってみましょう。
-
のどが渇く
-
口の中が乾く
-
頭痛、めまい
-
倦怠感、集中力の低下
-
尿の色が濃く、回数が少ない
-
肌の乾燥、ハリの低下
-
筋肉のけいれん
特に高齢者や子どもは、自分で「のどが渇いた」と感じにくい傾向があるため、周囲の人が気を配ることが大切です。
3月の脱水予防に効果的な対策
1. 意識的な水分補給
春先のまだ寒さが残る時期は、「のどが渇いた」と感じる前に、意識的に水分を取ることが重要です。起床時、就寝前、運動前後、入浴前後など、タイミングを決めて定期的に水を飲む習慣をつけましょう。
理想的な水分摂取量は1日1.5〜2リットルが目安です。ただし、一度に大量に飲むのではなく、こまめに少しずつ補給するのがポイントです。
2. 湿度管理
室内の湿度を40〜60%に保つことで、呼吸や皮膚からの水分喪失を防げます。加湿器を活用したり、濡れタオルを干すなどして、乾燥しすぎないよう工夫しましょう。
3. 食事からの水分摂取
食事にも水分は含まれており、特に野菜や果物、スープ類は良い水分源になります。水分を多く含む食材(きゅうり、トマト、みかん、イチゴなど)を積極的に摂ることで、自然な形で水分を補えます。
4. カフェインやアルコールの摂取に注意
コーヒーやお茶、アルコールには利尿作用があるため、摂りすぎると逆に水分を失いやすくなります。これらを飲む際には、同時に水も一緒に摂るよう心がけましょう。
脱水が進むとどうなる?重度脱水のリスク
脱水症状を軽視していると、やがて重度の脱水に陥ることもあります。重度脱水では以下のような症状が現れます。
-
意識の混濁、判断力の低下
-
血圧の低下、脈拍の上昇
-
筋肉の強直(こむら返りなど)
-
嘔吐、下痢
-
失神、ショック症状
特に高齢者は体内の水分保持力が低く、重度脱水になりやすいため注意が必要です。症状が重い場合は、速やかに医療機関を受診しましょう。
運動時の水分補給も忘れずに
気候がよくなり、運動を始める人も多い時期ですが、運動中は想像以上に汗をかいています。運動前、中、後にはしっかりと水分補給を行いましょう。
特にジョギングやウォーキング、ジムトレーニングを行う際には、以下のポイントを意識してください。
-
運動前にコップ1杯(約200ml)程度の水を飲む
-
運動中も15〜20分ごとに少量の水を口にする
-
運動後は失った分を補うため、体重の変化も目安に水分補給する
春の脱水は侮れない
「春に脱水?」と驚く方もいるかもしれませんが、まさに油断大敵な季節です。気温の変化に身体がまだ完全に順応していない時期だからこそ、体内の水分バランスが崩れやすくなっています。
また、花粉症の薬(抗ヒスタミン薬)には、口の渇きなどの副作用を引き起こすものもあり、知らず知らずのうちに脱水が進行している場合もあります。
まとめ:3月も水分補給を忘れずに!
春先の3月は、寒暖差や空気の乾燥、発汗量の増加などにより、意外にも脱水症状を起こしやすい時期です。「のどが渇いていないから大丈夫」と油断せず、日頃からこまめな水分補給を心がけましょう。脱水を予防することは、体調管理の第一歩でもあります。水分をしっかりと摂ることで、春を健康的にスタートしましょう!

アイズトータルボディステーションでは
体験トレーニングを募集しております。
- ダイエット
- ボディメイク
- 姿勢改善
- 健康増進
- 筋力アップ etc…
お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。
- なかなか一人ではできない。
- 何をしたらいいのか分からない。
- ダイエットがうまくいかない
- 一人でトレーニングできるようになりたい。
- 専門的な指導を受けてみたい。
是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。
お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店
アイズ基山駅前整骨院
【所在地】
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉532
JR基山駅構内
【営業時間】
月・水・木・土
10:00~21:00
火・金
10:00~22:00
【TEL】
0942-85-9787