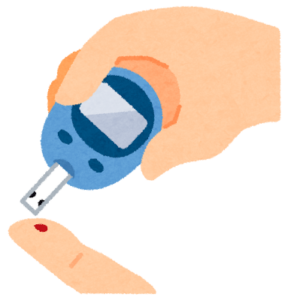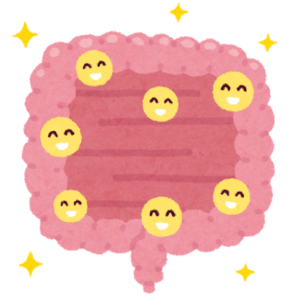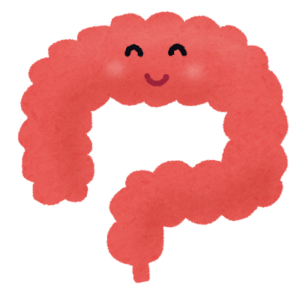タンパク質の重要性とその役割、1日に必要な摂取量
はじめに:タンパク質の基礎知識
タンパク質は炭水化物や脂質と並び、三大栄養素の一つです。人体において、タンパク質は筋肉や内臓、骨、皮膚、髪、爪などを構成する基本的な要素であり、生命維持に欠かせない栄養素です。人体の約20%はタンパク質でできており、エネルギーを供給する役割を持つだけでなく、組織の修復や生成、免疫機能の維持、代謝の促進など、体内の多くの重要なプロセスに関わっています。
この記事では、タンパク質の重要性、具体的な役割、そして1日にどれだけ摂取すべきかについて詳しく解説します。
1. タンパク質の重要性
1-1. 体の基本構造を支える
タンパク質は、筋肉や臓器、骨、皮膚、髪、爪といった、人体のあらゆる部位を構成する基本的な要素です。私たちの体は約10万種類ものタンパク質で構成されており、それぞれが特定の機能や役割を持っています。例えば、コラーゲンというタンパク質は皮膚や骨、腱を強くし、ケラチンは髪や爪を構成します。
このように、タンパク質は細胞や組織の修復と生成に欠かせないため、成長期の子供や、運動をしている人、ケガから回復する人にとって特に重要です。タンパク質が不足すると、体の修復機能が低下し、成長が遅れるだけでなく、筋肉量が減少し、疲労感が増すなど、健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
1-2. エネルギー供給源としての役割
タンパク質は、主に炭水化物や脂質の不足時に、エネルギー源として利用されます。1gあたり約4kcalのエネルギーを供給し、必要に応じて体内でエネルギーに変換されます。しかし、タンパク質の主な役割は筋肉や臓器などの体組織の維持と修復であるため、エネルギー源として使われるべきではありません。十分な炭水化物や脂質の摂取がなければ、体はタンパク質をエネルギー源として消費してしまい、筋肉量の減少や代謝の低下を引き起こす可能性があります。
2. タンパク質の主な役割
2-1. 筋肉の修復と成長
タンパク質の代表的な役割の一つが、筋肉の修復と成長を助けることです。運動や筋トレなどで筋肉にストレスがかかると、筋繊維が一時的に損傷を受けます。この時、タンパク質が体内で使われ、筋肉の修復を助けることで、筋肉は以前よりも強くなり、成長します。
特に運動後のリカバリーには、タンパク質の摂取が欠かせません。運動によって分解された筋肉を修復し、新たな筋肉を合成するためには、十分なタンパク質を摂取することが必要です。これが、筋肉量を増やしたいアスリートやボディビルダーがタンパク質の摂取に注力する理由です。
2-2. 酵素の生成
体内で起こる化学反応の多くは、酵素と呼ばれる特殊なタンパク質によって制御されています。酵素は、食べ物の消化や代謝、DNAの複製、細胞の修復など、生命活動を支える無数のプロセスに関与しています。
例えば、消化酵素は、食物中の栄養素を小さな分子に分解し、体がそれを吸収できるようにします。また、代謝酵素は、栄養素をエネルギーに変換し、体が効率的に機能するのを助けます。これらの酵素が正常に機能するためには、適切な量のタンパク質が必要です。
2-3. ホルモンの生成
ホルモンもタンパク質の一種で、体内のさまざまな機能を調整しています。例えば、インスリンは血糖値を調節し、成長ホルモンは体の成長と発達を促進します。また、甲状腺ホルモンは代謝率を管理し、エネルギーレベルや体温を調整する役割を担っています。
これらのホルモンが適切に生成されるためには、十分な量のタンパク質が必要です。ホルモンバランスが崩れると、体の機能に悪影響を与えることがあるため、ホルモンの生成をサポートするためにもタンパク質の摂取は欠かせません。
2-4. 免疫機能のサポート
タンパク質は免疫システムの維持にも重要です。抗体と呼ばれるタンパク質は、体内に侵入した細菌やウイルスと戦うために働きます。抗体が病原体に結びつき、感染を防ぐことで、体の健康を守ります。
もしタンパク質が不足すると、免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなることがあります。そのため、風邪やインフルエンザの季節には、体を守るために十分なタンパク質の摂取が重要です。
2-5. その他の役割
タンパク質は、体の水分バランスやpHバランスを保つ役割も担っています。例えば、アルブミンというタンパク質は血液中の水分を調整し、体内の水分が過剰に溜まるのを防ぎます。また、ヘモグロビンというタンパク質は、酸素を運ぶ役割を果たし、全身の細胞に酸素を供給します。
3. 1日に必要なタンパク質の摂取量
1日に必要なタンパク質量
除脂肪体重(Lean Body Mass)ベース
3-1. 除脂肪体重(Lean Body Mass)とは?
除脂肪体重(LBM)とは、体重から体脂肪を除いた筋肉、骨、臓器などの脂肪以外の組織を指します。この指標を基にタンパク質の必要摂取量を計算することで、体脂肪を含まない部分に対して適切な量のタンパク質を供給できるため、より正確な摂取目安が導き出せます。
タンパク質は主に筋肉を構築・修復するために利用されるため、体脂肪を除いた除脂肪体重を基準にした方が、効率的なタンパク質摂取量を計算できます。
3-2. 除脂肪体重ベースのタンパク質摂取量
一般的なガイドラインとして、除脂肪体重1kgあたりのタンパク質の推奨摂取量は以下のようになります。
除脂肪体重1kgあたり1.2〜1.5gのタンパク質: これは、筋肉量の維持や軽度な筋力トレーニングをしている人に推奨される範囲です。
除脂肪体重1.5〜2.0gのタンパク質: 筋肉量を増やしたい人、または強度の高い筋力トレーニングを行っているアスリート向けです。
3-3. 除脂肪体重の計算方法
除脂肪体重を求めるには、まず体脂肪率を知る必要があります。以下の手順で計算します。
体脂肪率を知る: 体脂肪率は、体組成計や体脂肪計を使って計測します。
除脂肪体重を計算する: 体脂肪率を元に、次の式で除脂肪体重を計算します。
除脂肪体重(kg)=体重(kg)×(1 − 体脂肪率)
例: 体重70kg、体脂肪率20%の場合
除脂肪体重 = 70kg × (1 − 0.20) = 70kg × 0.80 = 56kg
4. タンパク質を多く含む食品
タンパク質を効率的に摂取するために役立つ、タンパク質含有量が多い食品を紹介します。動物性・植物性の両方から選べる食品がありますので、バランスよく摂取するのが理想です。
動物性タンパク質が豊富な食品
鶏むね肉(皮なし)
100gあたり約23gのタンパク質
低脂肪で、高タンパクの代表的な食品。調理しやすく、筋トレ愛好者に人気です。
牛赤身肉
100gあたり約20〜24gのタンパク質
良質なタンパク質源で、ビタミンB群や鉄分も豊富。
卵
1個(約50g)あたり約6gのタンパク質
高品質のタンパク質を含み、全卵で摂取することでビタミンやミネラルも豊富。
魚(サーモン、マグロ、タラなど)
100gあたり約20〜25gのタンパク質
サーモンやマグロはオメガ3脂肪酸も含み、心臓の健康にも良いとされています。
ギリシャヨーグルト
100gあたり約10gのタンパク質
普通のヨーグルトよりタンパク質が多く、低脂肪で朝食や間食に最適。
カッテージチーズ
100gあたり約11〜14gのタンパク質
低カロリーかつ高タンパクで、ダイエットや筋トレのサポートに。
植物性タンパク質が豊富な食品
豆腐(木綿豆腐)
100gあたり約7〜8gのタンパク質
低カロリーでありながら、良質な植物性タンパク質を含み、料理のバリエーションも豊富。
納豆
1パック(約50g)あたり約8gのタンパク質
植物性タンパク質に加え、食物繊維やビタミンKも豊富。腸内環境を整える効果も。
レンズ豆
100gあたり約9gのタンパク質
食物繊維やミネラルが豊富で、スープやサラダに加えることで摂取しやすい。
ひよこ豆(ガルバンゾ)
100gあたり約19gのタンパク質(乾燥状態)
スープやサラダ、フムスなどの料理に使え、タンパク質や食物繊維が豊富。
アーモンド
100gあたり約21gのタンパク質
高タンパクで、ビタミンEやマグネシウムも含まれます。間食やサラダのトッピングに最適。
大豆ミート
100gあたり約20gのタンパク質
動物性の肉の代替品として注目される高タンパクな食材。ヴィーガンやベジタリアン向けの料理に使いやすい。
動物性タンパク質では、鶏むね肉や魚、卵が高品質なタンパク質源です。植物性では、豆類や豆腐、ナッツ類が豊富なタンパク質を提供します。これらの食品をバランスよく取り入れることで、筋肉の成長や維持、健康的な生活をサポートできます。
まとめ
タンパク質は、体の基本的な構造を支え、筋肉の修復と成長、酵素やホルモンの生成、免疫機能の維持など、多くの重要な役割を果たしています。1日に必要なタンパク質の量は、年齢や活動レベルによって異なり、特に運動量の多い人や高齢者には十分な摂取が推奨されます。タンパク質を多く含む食品をバランスよく摂取し、健康的な生活を送りましょう。

アイズトータルボディステーションでは
体験トレーニングを募集しております。
- ダイエット
- ボディメイク
- 姿勢改善
- 健康増進
- 筋力アップ etc…
お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。
- なかなか一人ではできない。
- 何をしたらいいのか分からない。
- ダイエットがうまくいかない
- 一人でトレーニングできるようになりたい。
- 専門的な指導を受けてみたい。
是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。
お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店
アイズ基山駅前整骨院
【所在地】
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉532
JR基山駅構内
【営業時間】
月・水・木・土
10:00~21:00
火・金
10:00~22:00
【TEL】
0942-85-9787