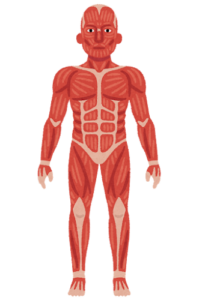冬の紫外線の特徴とその影響
冬になると紫外線への意識が薄れる方も多いのではないでしょうか。しかし、冬でも紫外線は降り注いでいます。実は、紫外線は年間を通して地上に届いており、特にUV-Aと呼ばれる波長の長い紫外線は、季節に関係なく安定して地表に到達します。このUV-Aは肌の奥深くまで届き、シミやしわの原因となる「光老化」を引き起こすことがあります。
一方、夏に多いとされるUV-Bは、冬になるとその量が減少するため、日焼け(炎症)のリスクは下がります。ただし、UV-Bがゼロになるわけではありません。特にスキー場や雪の多い地域では、雪による紫外線の反射率が高いため、油断は禁物です。
冬の紫外線が特に注意すべきポイント
紫外線の反射 冬の特徴として、雪が紫外線を反射することが挙げられます。反射率はなんと**80%**以上にもなり、直射日光を浴びなくても紫外線を受けるリスクがあります。これはスキーやスノーボードを楽しむ際に、顔や目へのダメージを大きくする要因となります。
長時間の露出 冬は寒さ対策として厚着をするため、肌の露出は少ないように感じますが、顔や手などは無防備になりがちです。また、冬の日差しは柔らかく感じるため、つい日差しの中で過ごす時間が長くなることもあります。
高地での紫外線強度 山岳地帯やスキー場では標高が高いため、紫外線量が増加します。標高が1000m上がるごとに、紫外線の強さは約10%増加するとされています。
冬の紫外線対策の基本
日焼け止めの使用 冬でも日焼け止めは必須です。夏用のSPF50ではなく、SPF20~30程度の低刺激の日焼け止めが適しています。顔だけでなく、首や手にも塗りましょう。
保湿対策を忘れずに 冬の乾燥した空気と紫外線の影響で、肌のバリア機能が低下しやすくなります。日焼け止めを塗る前に、しっかりと保湿クリームや乳液で肌を整えましょう。
リップケア 唇も紫外線の影響を受けやすい部分です。UVカット効果のあるリップクリームを使い、乾燥と紫外線ダメージから守りましょう。
帽子やサングラスの活用 雪の反射を考慮すると、紫外線対策としてつばの広い帽子やUVカットサングラスが効果的です。特にサングラスは目の健康を守るためにも必須です。
冬用のUVカットアイテム UVカット効果のある手袋やマスクも、寒さ対策と紫外線対策を兼ねて役立ちます。
冬の紫外線ダメージを軽減するためのスキンケア
日中のケア 外出時には日焼け止めを塗るだけでなく、数時間おきに塗り直す習慣をつけましょう。特に雪山やアウトドアで過ごす場合は、持ち運び用の日焼け止めを携帯すると便利です。
夜のケア 日中受けた紫外線ダメージをリセットするためには、抗酸化成分を含むスキンケア製品の使用が効果的です。ビタミンCやビタミンE配合の美容液やクリームを取り入れると良いでしょう。
紫外線対策のインナーケア 紫外線ダメージを軽減するために、抗酸化作用のある食べ物を摂取するのも有効です。例えば、ビタミンCを含む柑橘類や、βカロテンが豊富な緑黄色野菜を積極的に取り入れましょう。
冬に紫外線対策を怠るとどうなる?
紫外線対策を怠ると、以下のような問題が起こる可能性があります。
シミやそばかすの原因に 冬に受けた紫外線ダメージが蓄積され、春から夏にかけてシミやそばかすとして現れることがあります。
肌の乾燥と老化 紫外線は肌の水分を奪い、乾燥を悪化させます。また、コラーゲンを破壊するため、しわやたるみの原因にもなります。
免疫力の低下 紫外線を浴びすぎると、皮膚の免疫細胞がダメージを受け、肌荒れやニキビができやすくなる可能性があります。
冬の紫外線対策を日常に取り入れるポイント
習慣化する 日焼け止めを塗ることや、保湿ケアをすることを毎日のルーティンに組み込みましょう。
天気予報をチェック 冬でも紫外線量は天候に左右されます。晴天の日や雪が積もった日には、より念入りな対策が必要です。
スキンケア用品の見直し 冬の乾燥を考慮して、保湿効果の高いスキンケア製品を選びつつ、UVカット効果のあるものを積極的に活用しましょう。
まとめ
冬の紫外線は意外と見過ごされがちですが、肌に与える影響は無視できません。特にUV-Aの光老化リスクや雪による反射紫外線に注意が必要です。日焼け止めや保湿ケアを基本に、適切な対策を講じることで、冬の紫外線ダメージを最小限に抑えることができます。
これからの季節、スキーやスノーボードなどのアクティビティを楽しむ際にも、しっかりと紫外線対策を行い、健やかな肌を保ちましょう。

アイズトータルボディステーションでは
体験トレーニングを募集しております。
- ダイエット
- ボディメイク
- 姿勢改善
- 健康増進
- 筋力アップ etc…
お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。
- なかなか一人ではできない。
- 何をしたらいいのか分からない。
- ダイエットがうまくいかない
- 一人でトレーニングできるようになりたい。
- 専門的な指導を受けてみたい。
是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。
お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店
アイズ基山駅前整骨院
【所在地】
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉532
JR基山駅構内
【営業時間】
月・水・木・土
10:00~21:00
火・金
10:00~22:00
【TEL】
0942-85-9787