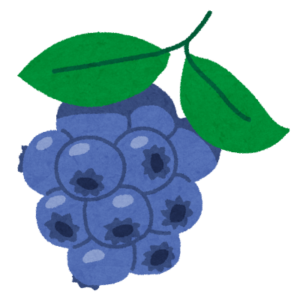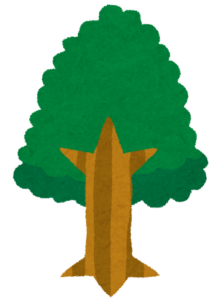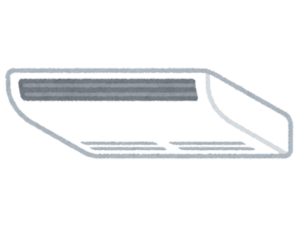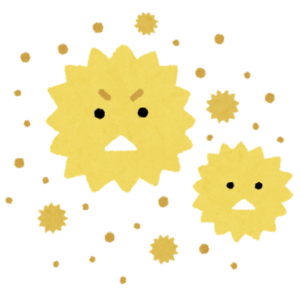5月特有の“眠気”は「メラトニン逆流現象」かもしれない:春の不調を科学的に解明する
春の陽気に包まれ、新しい生活が始まるこの季節。しかし、「なぜか眠い」「朝起きても疲れが取れない」といった不調を感じている人も少なくありません。特に5月は、「春バテ」や「五月病」といった言葉に象徴されるように、心身にさまざまな変調をきたしやすい時期です。実はこの春特有の眠気には、「メラトニン逆流現象」と呼ばれるホルモンのリズムの乱れが関係している可能性があります。
この記事では、メラトニン逆流現象の仕組みとその影響、さらに対策までを医学的な観点から詳しく解説します。
1. 春の眠気の正体:「メラトニン逆流現象」とは?
1-1 メラトニンの基本的な役割
メラトニンとは、脳の松果体という部位から分泌されるホルモンで、私たちの「体内時計」を調節する働きがあります。通常、夜になると分泌量が増え、眠気を誘導。朝になると分泌が止まり、覚醒へと導きます。
このホルモンは、主に光によって調整されます。夜間に暗くなることで分泌が始まり、朝日を浴びることで抑制されます。このサイクルが正しく保たれていることで、私たちは自然な睡眠と覚醒のリズムを維持できるのです。
1-2 「逆流」とは何か?
本来なら、朝に太陽光を浴びることでメラトニンの分泌は止まり、スッキリとした目覚めが得られます。しかし春先になると、体内のリズムがまだ冬のパターンを引きずっているため、朝になってもメラトニンの分泌が十分に抑制されず、血中濃度が高いままになります。
この「朝になってもメラトニンが残る」という状態が、「逆流現象」と呼ばれているものです。日中に本来抑えられるべき眠気が残ってしまい、頭がボーっとする、集中力が落ちる、体が重いなどの症状が現れます。
2. なぜ春に「メラトニン逆流現象」が起きるのか?
2-1 季節の変化と体内時計のズレ
春は日照時間が急激に延び、気温も上昇します。この環境変化は、私たちの体内リズムに大きな影響を与えます。特に、冬の生活で朝遅く起きていた人は、春の日差しに体がすぐに順応できず、体内時計がずれた状態になります。
また、日本では4月から新生活が始まる人も多く、生活リズムが乱れやすい時期でもあります。これもメラトニンの分泌リズムに影響を与え、朝の目覚めが悪くなり、結果として日中の眠気を引き起こす原因になります。
2-2 自律神経の乱れも関係
春は気圧の変動が激しく、自律神経にも大きな負担がかかります。自律神経は交感神経(活動)と副交感神経(休息)から成り、これらのバランスが崩れると、体温や睡眠、ホルモン分泌などがうまく調整されなくなります。結果として、メラトニンのリズムも乱れてしまうのです。
3. 春の眠気に拍車をかける要因
3-1 花粉症による眠気
春のもう一つの厄介者は花粉症です。花粉症の薬(抗ヒスタミン薬)には、眠気を誘発する副作用があるものが多く、これが日中の眠気を強めてしまいます。さらに、花粉症の症状そのものが睡眠の質を下げるため、朝起きても疲れが取れていないという状況になりやすいのです。
3-2 精神的ストレス
4月から新生活が始まり、5月に入る頃にはストレスや疲労が蓄積しやすくなります。この「五月病」と呼ばれる状態は、実はうつ病の一歩手前であることも多く、特に朝の起床困難や日中の強い眠気が共通症状として現れます。
4. メラトニン逆流現象への具体的対策
4-1 朝日をしっかり浴びる
朝の太陽光は、メラトニンの分泌を止め、セロトニンという覚醒系ホルモンの分泌を促進します。特に起床後30分以内に15〜30分ほど外に出て日光を浴びることが推奨されています。これにより体内時計がリセットされ、日中の眠気も抑えられます。
4-2 生活リズムを整える
毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起きることが体内時計を整える最も基本的な方法です。休日の「寝だめ」は体内時計を狂わせる原因になるため、平日と同じリズムで過ごすことが望ましいです。
4-3 食生活の改善
メラトニンの前駆体である「セロトニン」は、必須アミノ酸であるトリプトファンから作られます。トリプトファンを多く含む食品(バナナ、ナッツ、大豆製品、卵、乳製品など)を意識的に摂取することで、メラトニンの正常な分泌を促すことができます。
4-4 運動習慣をつける
軽い有酸素運動(ウォーキングやストレッチなど)は自律神経を整えるのに効果的です。特に午前中に体を動かすことで、体温リズムとホルモンの分泌リズムが整いやすくなります。
5. 医療機関を受診すべき場合
眠気が日常生活に支障をきたすレベルで続く場合は、睡眠障害やうつ病、過眠症などの病気が隠れている可能性もあります。以下のような症状が2週間以上続く場合は、専門医に相談しましょう。
-
日中に耐えられない眠気がある
-
頭が重く集中力が続かない
-
食欲低下や気分の落ち込みを感じる
-
睡眠中にいびきや呼吸停止の兆候がある
まとめ
5月の特有の眠気には、「メラトニン逆流現象」というホルモンの乱れが深く関係しています。春の環境変化は心身に大きな負担をかけ、自律神経や体内時計のバランスを崩しやすくなります。その結果として、日中の強い眠気やパフォーマンス低下が現れるのです。
対策としては、朝の光をしっかり浴びること、規則正しい生活を保つこと、トリプトファンを含む食品の摂取や運動の習慣化が効果的です。そして、眠気が続く場合は、早めに医療機関に相談することが大切です。
この春は、身体と心のサインに耳を傾け、賢く乗り越えていきましょう。
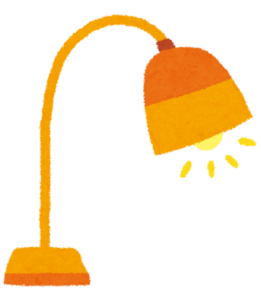
アイズトータルボディステーションでは
体験トレーニングを募集しております。
- ダイエット
- ボディメイク
- 姿勢改善
- 健康増進
- 筋力アップ etc…
お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。
- なかなか一人ではできない。
- 何をしたらいいのか分からない。
- ダイエットがうまくいかない
- 一人でトレーニングできるようになりたい。
- 専門的な指導を受けてみたい。
是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。
お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店
アイズ基山駅前整骨院
【所在地】
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉532
JR基山駅構内
【営業時間】
月・水・木・土
10:00~21:00
火・金
10:00~22:00
【TEL】
0942-85-9787