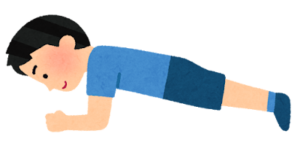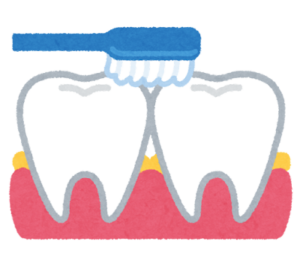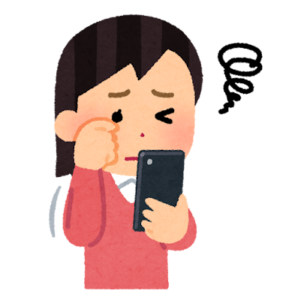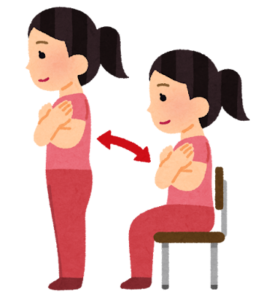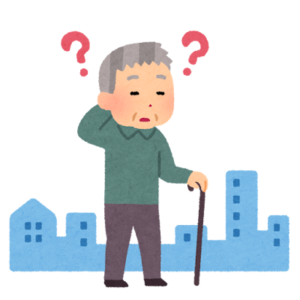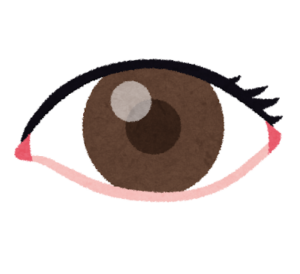1.世界患者安全の日(9月17日)
テーマ:医療ミス防止、医療の質、安全な診療体制
切り口:患者の自己管理力、正しい情報の理解力(ヘルスリテラシー)向上、セカンドオピニオンの活用法
はじめに
毎年9月17日は「世界患者安全の日」。これは World Health Organization(WHO)が定めた、患者安全(Patient Safety)を世界的に促進するための啓発日です。 世界保健機関+2patient-safety-day.org+2
医療の現場では、診療・治療・薬剤・手術・検査・ケアなど様々なヒト・設備・システムが関わっており、その複雑さゆえに「ミス」や「ヒヤリ・ハット」「不適切な診断・治療」「医療機器の誤使用」「転倒・転落・院内感染」など、患者にとっての危害(ハーム)が起こり得ます。例えば、入院中の患者のうち、ある国では10人中1人が医療の過程で何らかのハームを被るという報告もあります。 ウィキペディア+1
そのため、医療の質・安全な診療体制の確立は、世界中どの国でも重要な公衆衛生・医療政策の課題です。
この記念日を機に、今回は「患者側(利用者側)」の視点にフォーカスをあて、特に 「自己管理力」「ヘルスリテラシー(正しい情報を理解・活用する力)」「セカンドオピニオンの活用」 という切り口で、医療ミス防止・医療の質向上・安全な診療体制のために私たち個人ができることを整理します。
医療ミス・医療過誤・診療の質とは
まず、医療ミスや医療ハーム、医療の質・安全という概念を整理しておきましょう。
- 医療ミス/医療ハーム:医療を受ける過程で、本来起きるべきでない誤り・逸脱・事故・有害事象が発生し、患者に損害(身体的・精神的・経済的)をもたらす状態。 ウィキペディア+1
- 医療の質(Quality of Care):医療が、「安全である」「有効である」「患者中心である」「タイムリーである」「効率的である」「公平である」という観点で提供されているか、という指標。
- 安全な診療体制:ヒト(医療者、患者、家族)、設備・機器、システム・プロセス(診療フロー・チェックリスト・情報共有)などが整備され、エラーの起こりにくい体制が構築されていること。
このように、医療を受ける者も、医療を提供する者も、安全・質の高い医療を目指すための「対策・仕組み・意識」が求められています。
例えば、2025年版の世界患者安全の日では、「Safe care for every newborn and every child/Patient safety from the start!(生まれたときから、子どもすべてに安全なケアを)」というスローガンが掲げられています。つまり、生まれたばかりの新生児・乳幼児に対して、安全かつ質の高いケアを提供することがテーマです。 世界保健機関+1
日本でも、厚生労働省や各自治体が「医療安全」「医療の質」「患者参加」などの観点を強化しており、患者の側も「自分の医療に関与する」時代となっています。
患者の自己管理力がなぜ重要か
医療安全・質の観点から、患者自身が「自分の健康・診療に関わる主体」であることが非常に重要です。これを「自己管理力」と捉えることができます。なぜこの自己管理力が医療ミス防止・安全な診療体制に関連するのか、以下整理します。
1.自分の体・病気・治療を知る
例えば、持病がある人、複数の医療機関・薬を利用している人、高齢者・子ども・障害のある人は、医療において「自分の病状・治療歴・薬(アレルギー・副作用)・検査値」などを把握しておくことが、安全な医療に繋がります。
・もし医療者側が患者の持病・服薬状況・アレルギーを把握していなければ、重複薬・相互作用・誤薬のリスクが高まる。
・患者自身が「この薬ってなんのため?」「この検査結果はどういう意味?」と理解していないと、医療者の説明ミスや情報伝達ミスで、適切な意思決定が行われない可能性があります。
・自己管理ができている患者は、症状が変化した時に早期に気づき、医療機関を受診・相談できるため、急変・悪化・合併症を防ぎやすい。
こうした意味で、患者の「自分ごととしての医療参加」が、医療ミス・不安全事象のリスクを低くすることに結びつきます。
2.治療の継続・フォローアップの質を高める
病気になった後、治療を受けるだけではなく、定期的な検査・フォローアップ・薬の継続・生活習慣の改善などが重要です。自己管理力が高い人ほど「指示どおり薬を飲む」「予約通り通院する」「検査値を把握する」「体重・血圧・血糖などを記録・管理する」などが実践でき、結果として医療の質が高まります。
逆に、自己管理が十分でないと、治療中断・検査未実施・症状悪化・合併症発症といった流れになりやすく、それが医療機関の負荷増・ミスの温床ともなり得ます。
3.診療におけるコミュニケーションの質を上げる
医療者と患者(およびその家族・介護者)とのコミュニケーションが円滑であることは、安全な診療体制において不可欠です。患者側が自己管理できていると、以下のようなメリットがあります。
- 事前に疑問・不安を整理しておき「この説明でいいのだろうか?」と質問できる。
- 診療時に、飲んでいる薬・サプリ・アレルギー・他院受診歴などを的確に伝えられる。
- 医療者が出した説明・治療方針を患者自身が理解・納得してから進める(=インフォームドコンセントが実質的になる)。
このように、患者側が積極的に関与できる自己管理力が、安全かつ質の高い診療につながるのです。
正しい情報の理解力(ヘルスリテラシー)を高める
続いて、「ヘルスリテラシー(Health Literacy)=医療・健康に関する情報を正しく理解し、活用する力」について解説します。これも、医療ミス防止・診療の質向上において極めて重要です。
ヘルスリテラシーとは何か?
ヘルスリテラシーとは、健康・医療・疾病・リスク・予防・治療・検査などに関する情報を“読み解き・理解し・判断して・活用”する力を指します。単に「情報を聞く」・「資料をもらう」だけでなく、「その情報の意味を理解し、自分の生活・状況に即して活かす」ことが含まれます。
例えば、検査結果が「血糖値120 mg/dL」と出たとしても、「これは正常の範囲か?高めか?治療対象か?生活習慣の改善で十分か?」と理解できなければ、ただ数値を聞いたまま放置されてしまう可能性があります。
なぜヘルスリテラシーが医療安全に関係するのか?
- 医療や検査・治療には専門用語・数値・リスク・利益・副作用・代替案など、必ずしも誰もが理解しやすいものではありません。理解できないと、誤った判断・誤解・治療中断・不用意な自己判断(「◯◯がよかったらしいから薬やめよう」など)につながる可能性があります。
- 医療機関では短時間で説明が終わってしまうことも多く、患者が「わかったつもり」「聞き流した」状態だと、実際には理解不足であることがあります。そのため、医療者側も「患者が理解できたか」を確認する必要があります。
- 患者が説明を理解していると、自己管理(前述)・治療継続・適切な受診・疑問質問・副作用報告など、「能動的な医療参加」が可能になります。これが医療過誤・ミス・事故の防止につながります。
- 逆に、ヘルスリテラシーが低いと、誤った自己判断(ネット情報だけで判断する・複数の医療機関で情報が食い違い、どこを信じていいか分からない)などを招きやすく、医療安全の観点からリスクが高くなります。
ヘルスリテラシーを高めるためのポイント
- 疑問を持つ・質問する習慣をつける
– 医療者の説明で「これはどういう意味ですか?」「この検査値が予想より高いってどういうことですか?」「薬の副作用はどれくらいありますか?」など、自分の言葉で質問できるようにしましょう。
- 資料・検査結果・処方内容を記録・保存する
– 自分のカルテ・検査値・服薬歴・アレルギー・他院受診歴などをノートやスマホメモに残しておくと、複数の医療機関を利用している場合でも情報の抜け・重複を防げます。
- 信頼できる情報源を持つ
– ネット・SNS・ブログなどに健康・医療情報が溢れていますが、「根拠(エビデンス)があるか」「信頼できる機関(医療機関・学会・公的機関)か」「広告・PR・販売目的ではないか」を見極める視点を持ちましょう。
- 自分の状態を知る(基礎データを把握)
– 身体計測(身長・体重・体脂肪)、血圧、血糖、脂質、腎機能、肝機能、既往歴・家族歴など「自分当事者情報」を整理して、自分がどのリスクにさらされているかを把握しましょう。
- 医療者に積極的に参加する態度を持つ
– 「受け身」ではなく、「治療・検査・説明・フォローアップ」に対して自分の意見・希望・疑問を伝えることで、医療提供側と双方向のコミュニケーションが生まれ、安全性が高まります。
このように、ヘルスリテラシーを高めることは、ただ「教育する・知識を持つ」というより、「自分の医療・健康を管理・活用できる力を持つ」ということです。これが、医療ミス防止・安全な診療体制確立において、患者・医療者双方にとって鍵となります。
セカンドオピニオンの活用法
続いて、「セカンドオピニオン(Second Opinion)」の活用という観点から、安全・質の高い医療を受けるためにどう患者側が動けるかを整理します。
セカンドオピニオンとは?
セカンドオピニオンとは、ある診断・治療方針・手術などについて、主治医の意見以外に、別の医師・施設・専門家に意見を求めることを指します。治療の選択肢を確認・比較するという意味で、患者の権利として推奨される場合もあります。
なぜ活用すべきか?
- 診断・治療方針が一つではない場合、別の視点・専門家の意見を聞くことで、より最適な方針を選択できる可能性があります。
- 主治医の説明が十分でなかったり、治療内容が複雑だったりする場合、別の医師から違った説明を受け知識を深めることで、納得して治療に臨めます。
- セカンドオピニオンを通じて患者自身が「納得・理解」できるかどうかを確認でき、それが治療中・療養中の自己管理・受診行動・フォローアップにもプラスになります。
- また、誤診・不要な手術・過剰治療・適切でない治療を避けるという観点でも、セカンドオピニオンは安全性を高める役割があります。
セカンドオピニオン活用のポイント
- 主治医に率直に相談する
– 「別の意見を聞きたいのですが」など、主治医にセカンドオピニオンの意向を伝えましょう。医療機関・主治医によっては、相談窓口・紹介先・資料提供をしてくれるところもあります。
- 準備しておく情報を整理する
– 現在の診断書、検査データ(コピー)、治療方針、薬・副作用履歴、経過記録などを整理し、別の医師に見せられるようにします。自分自身でも「こういう治療を勧められました」「この選択肢をどう思いますか?」と質問できるように整理しておくと良いです。
- 専門医・大きな医療機関を検討する
– 特に手術・難治疾患・合併症がある場合、専門医・大学病院・専門施設(セカンドオピニオン外来がある病院)を検討するのが一般的です。紹介状・予約・費用(保険適用・自由診療)を確認しておきましょう。
- 情報を比較・検討する
– 複数の意見を聞いた場合、治療のメリット・デメリット・リスク・費用・経過観察の必要性などを整理して比較します。治療方針を決めた後、自分がその方針に納得できているかどうか確認しましょう。
- 治療開始後もフォローアップを怠らない
– セカンドオピニオンを受けた後でも、治療経過を記録し、疑問が出てきたら主治医・担当医に相談・情報共有を継続します。治療方針が途中で変更になることもあります。
セカンドオピニオンの活用が「安全な診療体制」につながる
・別の医師の意見を聞くことで、治療選択肢の網羅性が高まり、過剰治療・不適切治療の可能性を低くできます。
・患者自身が情報を整理・比較することで、医療提供側とのコミュニケーションが深まり、説明ミス・理解不足・誤解のリスクが減ります。
・医療者側にも「第三者の視点が入る」ことで、診療方針の検討・見直し・チーム医療の強化が促され、安全・質の高い診療につながります。
・結果として、医療ミス・不適切ケア・ハームの発生を減らし、患者が安心して医療を受けられる環境が整いやすくなります。
実践例・習慣化のヒント
上記の観点を日常生活から実践していくためのヒント・習慣化のポイントを挙げます。
- 診療前に「質問リスト」を作る
診察前に「聞きたいこと」「不安なこと」をメモしておきましょう。例えば「この薬の目的・副作用」「検査異常の意味」「治療をしないという選択肢はあるか?」など。
- 検査結果・薬歴を自分で保管・要約しておく
例えばスマホ・フォルダに「検査年月/項目/結果/主治医コメント」を保存し、次回受診時に医療者に提示できるように。
- 医療機関を横断利用しているなら、主治医以外の意見も定期的に検討する
例えば、手術前・転院前・治療方針に疑問があるときにはセカンドオピニオン外来を利用する。
- 説明を受けたあと、「(自分なりに)この説明を言い換えてみる」
例えば「この薬は〇〇のために1日1錠です。副作用は□□です。疑問が出たら次回までに聞いておきます」と自分の言葉でまとめると理解が深まります。
- 定期的に自分の「医療・健康カルテ」を見返す
過去の検査・受診・服薬を振り返ることで、「あれ?この薬いつから?」「この検査値この前より上がってる?」など、自分の健康状態にアンテナを張る習慣になります。
筋トレ・生活習慣との関連性(補足)
本記事の主題「健康・筋トレ・生活習慣」という観点から、医療安全・医療の質の観点に筋トレ・運動習慣がどう関わるか、補足的に整理します。
- 運動・筋トレ習慣を持つ人は、血圧・血糖・脂質・心肺機能などの改善傾向が見られ、病気の予防・治療継続に有利です。つまり、疾患発症・進行・合併症のリスクを下げ、医療機関の負荷も減らすという意味で「安全な医療生活」に資すると言えます。
- 自分の運動・健康データ(筋力、歩数、血圧変化など)を把握していると、治療や検査の際に「私は普段、このくらい動いています」「最近運動量が落ちてますが、関係ありますか?」など医療者に説明できます。これも自己管理力・ヘルスリテラシーの一環です。
- また、運動中に体調変化・ケガ・不調を感じた時点で自己判断せず、医療機関・専門家に相談する習慣があると、運動によるトラブル→医療ミス的リスク(例:自己判断で無理に継続して症状を悪化させる)を減らすことにつながります。
まとめ
・「世界患者安全の日」は、医療を受ける者・提供する者双方にとって、安全・質の高い医療の提供・受療を促す重要な啓発日です。
・特に患者の側として、「自己管理力」「ヘルスリテラシー」「セカンドオピニオン活用」という観点で動けることが、安全な診療体制・医療ミス防止に直結します。
・加えて、日常生活における運動(筋トレ含む)・健康習慣を意識することが、医療の質・安全性を高める土台となります。
・ぜひこの機会に、自分自身の受療態度・情報理解・生活習慣を振り返り、「次の受診・検査・治療」に備えてみてください。

アイズトータルボディステーションでは
体験トレーニングを募集しております。
- ダイエット
- ボディメイク
- 姿勢改善
- 健康増進
- 筋力アップ etc…
お客様の目的・目標に沿ったトレーニングを提供させて頂きます。
- なかなか一人ではできない。
- 何をしたらいいのか分からない。
- ダイエットがうまくいかない
- 一人でトレーニングできるようになりたい。
- 専門的な指導を受けてみたい。
是非一度、体験トレーニングを受けてみてはいかがでしょうか。
お問合せお待ちしております。

アイズトータルボディステーション基山店
アイズ基山駅前整骨院
【所在地】
〒841-0201
佐賀県三養基郡基山町小倉532
JR基山駅構内
【営業時間】
月・水・木・土
10:00~21:00
火・金
10:00~22:00
【TEL】
0942-85-9787